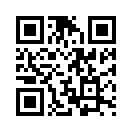2015年10月02日
ての争いは
「どんな仕事をしてきたのですか」
「あの藩のなかで、百姓|一《いっ》|揆《き》があったらしい。それをよく調べるようにとの命を受けました。たいしたこともなくおさまっていましたが、あったのは事実。それを報告に帰るところです……」
「しかし、隠密の仕事は、|外《と》|様《ざま》大名の動静をさぐるのが主でしょう。あの藩は、幕府に忠実な譜代の大名。小さな百姓一揆なんかについて、わざわざ調べることもないはず……」
「それが命令だったのです。老中筆頭からの命令となると、やらなければなりません」
「あなたは、いま眠いでしょう」
「はい……」
「はりつめた気分で仕事をしたので、疲れたのです。ぐっすり眠って目ざめると、いまの話はすっかり忘れ、すがすがしさがよみがえります」
三人は江戸の屋敷に戻る。なぞめいた隠密の動き。なにがどうなっているのだろう。みな、考えつづけだった。
そのうち、屋形忠三郎が幕府の人事についてのうわさを聞いてきた。
「しばらくぶりで、むかしの同僚に会って、話をしてきた。このあいだ隠密の入りこんだ藩のことを聞いてみた。あの藩主は、五万石の譜代大名。殿さまは大坂城代の地位にあったそうだ。それが、このあいだ不意にお役ご免になったという。領内の取締り不行き届きが理由だ。そ
れを指摘されると、お受けする以外になかったとか……」
「どういうことなのです、それは」
「幕府のなかで昇進するのには、それなりの順序があるのだ。最初はさまざまな役につくが、才能をみとめられると、奏者番になる。それから寺社奉行。つぎに、若年寄、大坂城代、京都所司代などをやる。それらの任をうまくはたすと、老中に進める。これがきまりなのだ」
「すると、あの藩主は、老中になれずじまいというわけですね。さぞ残念でしょうな」
「そりゃあ、そうだ。老中といえば、幕府のなかで最も権力ある地位。譜代のものなら、だれでもなりたがる。みなに恐れられ、うやまわれ、とどけ物も多いし、こんないごこちのいい地位はない。それをめぐっ、はげしいものだ」
「そういえば、尾形さんのかつての主君、奏者番になりそこないましたね」
「そうだった。うむ。なるほど。もしかしたら……」
ただならぬ表情になる。
「なにを思いついたのです」
「あの時、ばくち場へ案内してくれた町人のことだ。気になっていた。あまりにもつごうよく、奉行所の手入れがあった。密告されたのだろう。やつが隠密の手先、あるいは隠密そのものだったかもしれぬ……」
「それをたねに、殿さま、出世の道からはずされてしまった。逃げたとはいうものの、若殿がそこにいたことを知られたのでしょう」
ついに尾形忠三郎は、こぶしを振りあげ、大声でわめいた。
「なんということだ。老中筆頭が隠密を使って、気に入らぬ将来の競争相手を芽のうちにつみ取り、自分の地位の安泰をはかっているとは。人物や才能が評価されかける前に、つまらぬことを表ざたにし、いやおうなしに退かせてしまう。将軍がなさるのならまだいいが、隠密を使
えるということで、老中筆頭がそれをやるとは……」
Posted by orae at 15:23│Comments(0)