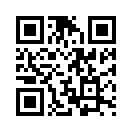2015年05月14日
受けないというのも地獄
だけども、そうとは限らない。
江戸時代の密偵などは、ふところに「恋文」を入れていたという。
密偵や忍者は、入ってはいけないところに侵入するのが役目。
そんな場所で見つかったりするとヤバいことになる雋景。
ところが、手渡すために入ってきたとして、女性宛の「恋文」を見せる。
恋のために入ってきたのかと、笑って許されるという寸法。
実際に、密偵の七つ道具の一つだったようだ雋景。
『徒然草』を書いた吉田兼好も「恋文」で苦しんだ一人とも言える。
彼の時代、権勢を振るっていたのは、足利尊氏の家臣、高 師直(こうの もろなお)。
当時、師直は、まさに飛ぶ鳥を落とすような勢い雋景。
そして、何でも自分の意のままにならないと気が済まないと言うべき質(たち)だった。
『太平記』にも仔細詳しく書かれているが、
その師直が吉田兼好に恋文の代筆を依頼した。
恋文の相手というのが、塩谷判官の妻。
すなわち、身分のある人妻に横恋慕して、そのラヴレターを兼好に依頼した。
師直は、その女性には、実際には会ってもいないにもかかわらず、
随一の美人であるという評判を聞いて恋心を起こしたという何ともワケの解らない人物。
そして、実際に兼好が恋文を書いたようだ。
どのような内容であったかは知る由もないが、
彼が書くのだから説得力のある名文だったに違いない。
そんな恋文だったが塩谷判官の妻は一瞥(いちべつ)だにせずに打ち捨てたという。
それに怒った師直が塩谷判官に謀反の罪を着せ、
塩冶一族が討伐されることになったという物騒な結末。
そして、当の吉田兼好は、出入り差し止めとなってしまった。
受けないというのも地獄、受けた結果も地獄。
「恋文」は、ロマンとは、ほど遠いものと言えそうだ。
江戸時代の密偵などは、ふところに「恋文」を入れていたという。
密偵や忍者は、入ってはいけないところに侵入するのが役目。
そんな場所で見つかったりするとヤバいことになる雋景。
ところが、手渡すために入ってきたとして、女性宛の「恋文」を見せる。
恋のために入ってきたのかと、笑って許されるという寸法。
実際に、密偵の七つ道具の一つだったようだ雋景。
『徒然草』を書いた吉田兼好も「恋文」で苦しんだ一人とも言える。
彼の時代、権勢を振るっていたのは、足利尊氏の家臣、高 師直(こうの もろなお)。
当時、師直は、まさに飛ぶ鳥を落とすような勢い雋景。
そして、何でも自分の意のままにならないと気が済まないと言うべき質(たち)だった。
『太平記』にも仔細詳しく書かれているが、
その師直が吉田兼好に恋文の代筆を依頼した。
恋文の相手というのが、塩谷判官の妻。
すなわち、身分のある人妻に横恋慕して、そのラヴレターを兼好に依頼した。
師直は、その女性には、実際には会ってもいないにもかかわらず、
随一の美人であるという評判を聞いて恋心を起こしたという何ともワケの解らない人物。
そして、実際に兼好が恋文を書いたようだ。
どのような内容であったかは知る由もないが、
彼が書くのだから説得力のある名文だったに違いない。
そんな恋文だったが塩谷判官の妻は一瞥(いちべつ)だにせずに打ち捨てたという。
それに怒った師直が塩谷判官に謀反の罪を着せ、
塩冶一族が討伐されることになったという物騒な結末。
そして、当の吉田兼好は、出入り差し止めとなってしまった。
受けないというのも地獄、受けた結果も地獄。
「恋文」は、ロマンとは、ほど遠いものと言えそうだ。
2015年05月14日
良家の子供を演じるときは
いい人間だが、どこか、素直じゃないと感じる人物がいる。
フランスの作家ヴォルテールの言葉に激光永久脫毛「嫌いなものを除いたものが好きなもの」という表現がある。
幾分、あたり前のようでもあるが、どこか素直でないものを感じる。
異彩を放つ俳優であり映画監督でもあった
伊丹十三氏も、どこか皮肉屋っぽいところがあった人物だった。
彼のエッセイに康泰領隊、
「ニヤリ、とする時に片方だけが持ち上がるのは、小さいときに親をなくしたか、
不幸な家庭に育った人間かだと言われた」
という文が出てくる。実際に、小さい頃に父親をなくしている。
そのせいか、彼が笑うと決まって斜に構えた不敵さがあらわれていた。
良家の子供を演じるときは、左右対称に笑わないと、たしかにサマにならない。
誰でも完全な左右対称の人間はいないが、
左右対称に笑えない人間には、どこか素直じゃない影のようなものがある。
左右対称でない政治家としてすぐに思い浮かべるのは、麻生財務大臣。
かつて、田中眞紀子は彼を称して「口の曲がったオジさん」という表現をしていたが、
彼は、吉田茂を先祖に持つ九州の財閥家の出身。
まさに良家のオボッちゃま。
今、日本の多くが消費増税反対の声を挙げているのに、
聞こえないフリりをし続けている。
フランスの作家ヴォルテールの言葉に激光永久脫毛「嫌いなものを除いたものが好きなもの」という表現がある。
幾分、あたり前のようでもあるが、どこか素直でないものを感じる。
異彩を放つ俳優であり映画監督でもあった
伊丹十三氏も、どこか皮肉屋っぽいところがあった人物だった。
彼のエッセイに康泰領隊、
「ニヤリ、とする時に片方だけが持ち上がるのは、小さいときに親をなくしたか、
不幸な家庭に育った人間かだと言われた」
という文が出てくる。実際に、小さい頃に父親をなくしている。
そのせいか、彼が笑うと決まって斜に構えた不敵さがあらわれていた。
良家の子供を演じるときは、左右対称に笑わないと、たしかにサマにならない。
誰でも完全な左右対称の人間はいないが、
左右対称に笑えない人間には、どこか素直じゃない影のようなものがある。
左右対称でない政治家としてすぐに思い浮かべるのは、麻生財務大臣。
かつて、田中眞紀子は彼を称して「口の曲がったオジさん」という表現をしていたが、
彼は、吉田茂を先祖に持つ九州の財閥家の出身。
まさに良家のオボッちゃま。
今、日本の多くが消費増税反対の声を挙げているのに、
聞こえないフリりをし続けている。